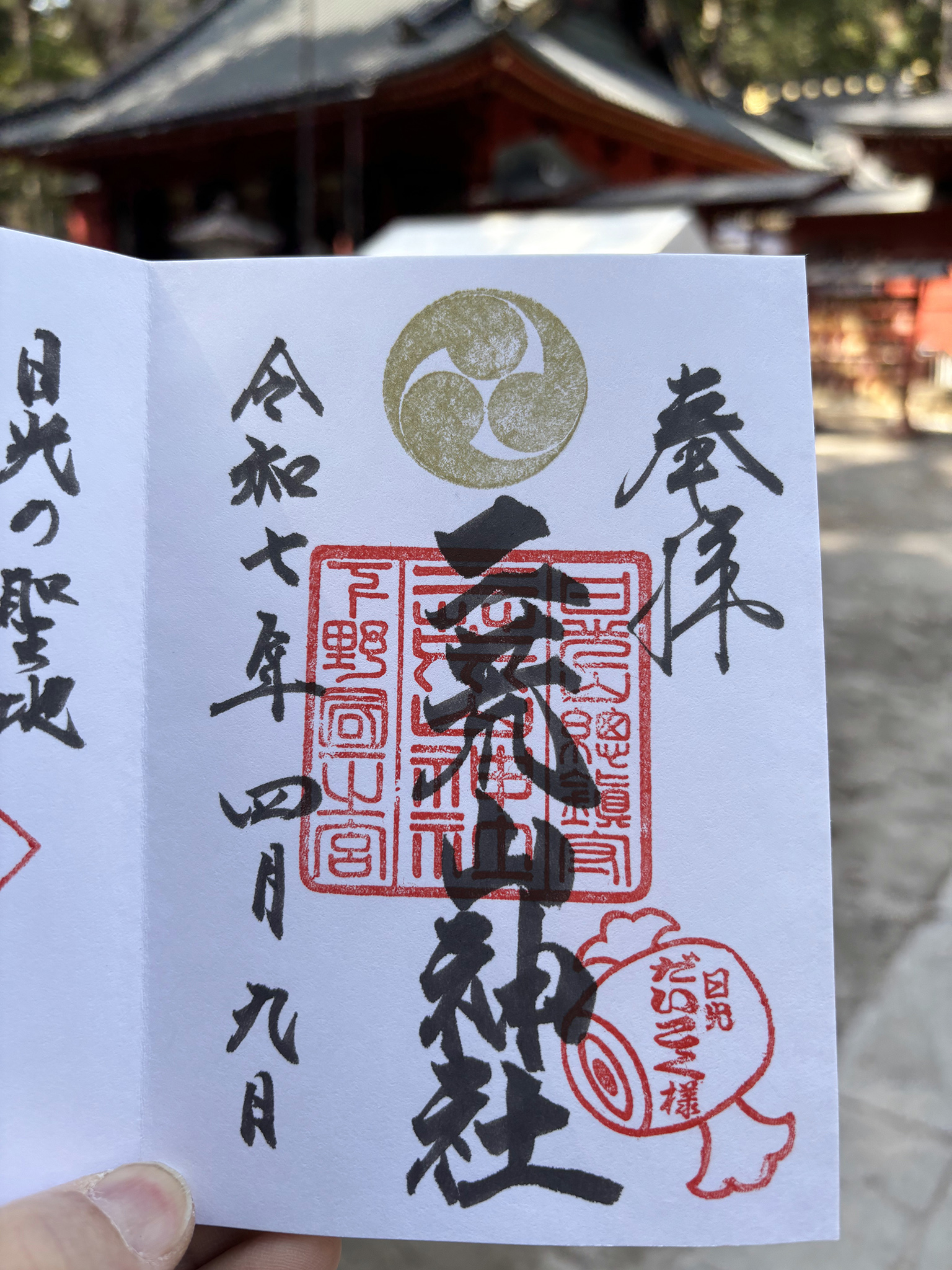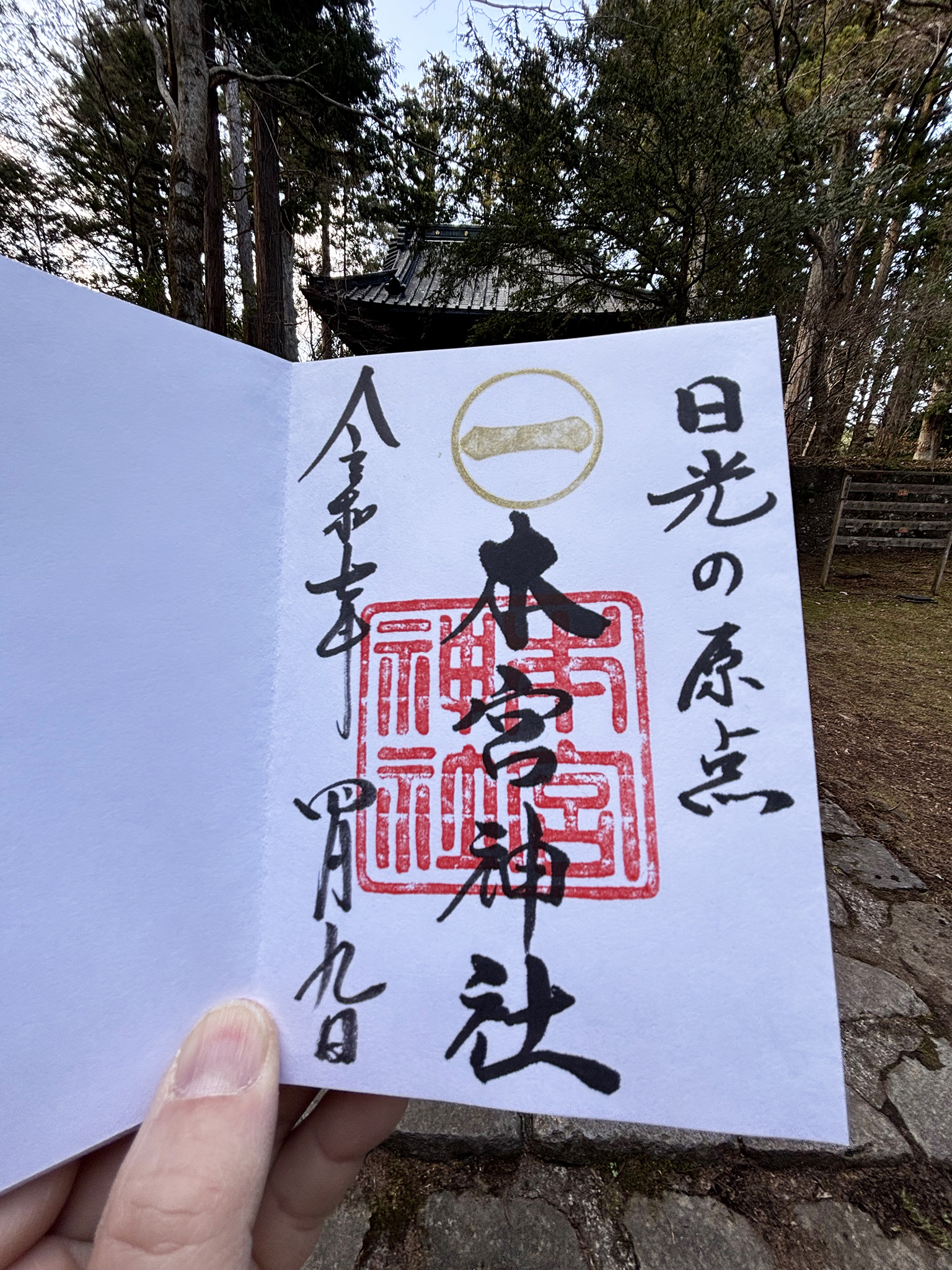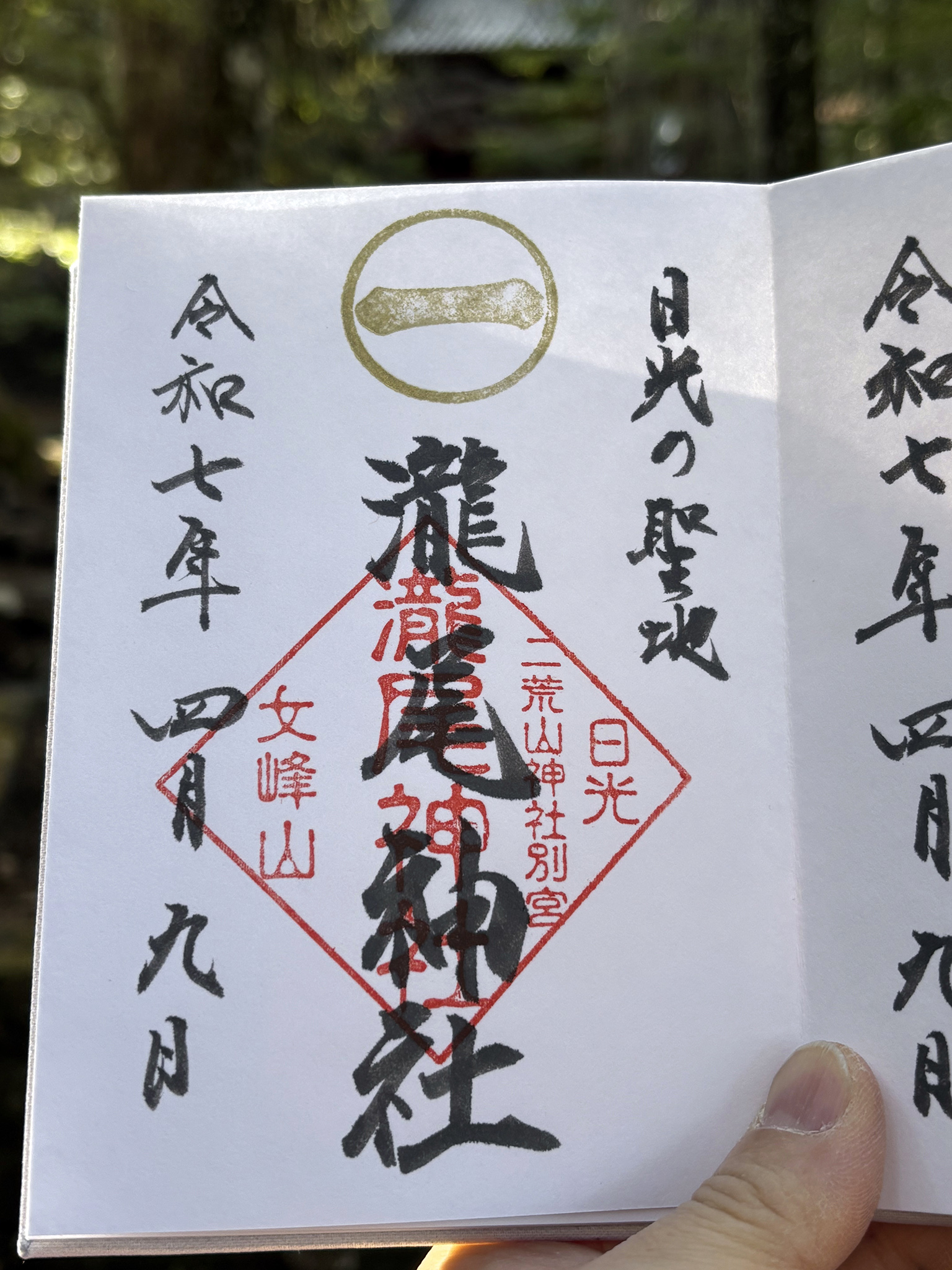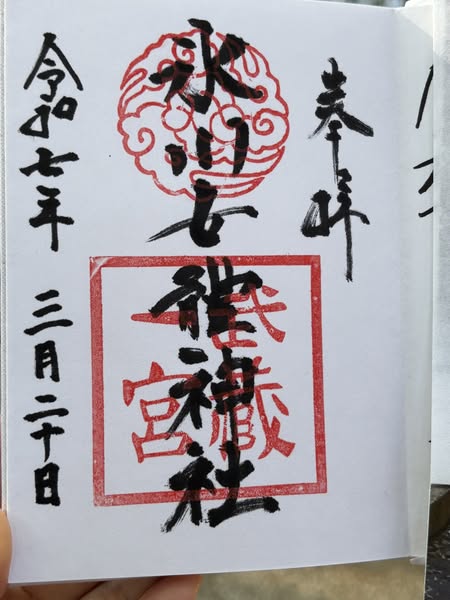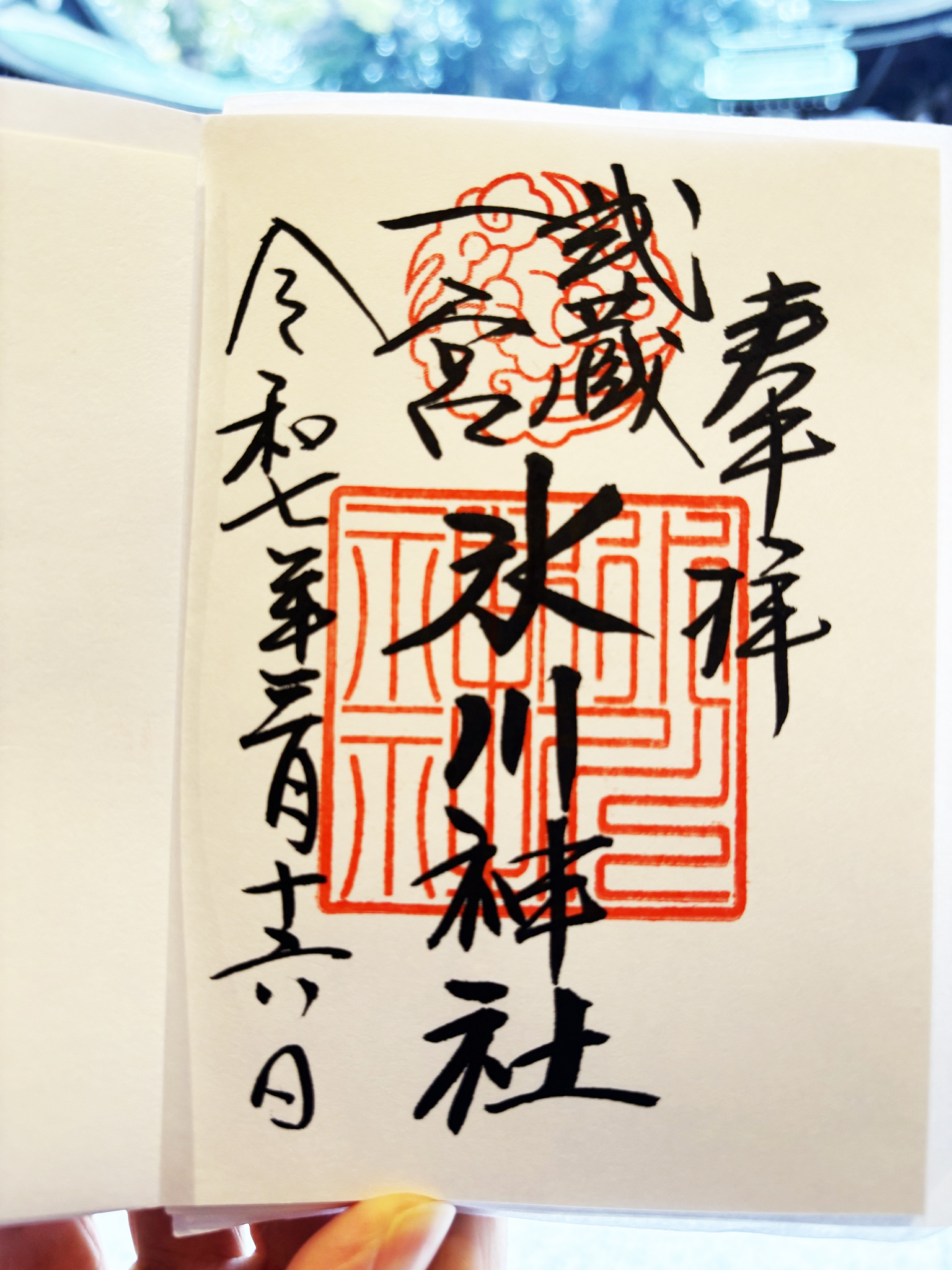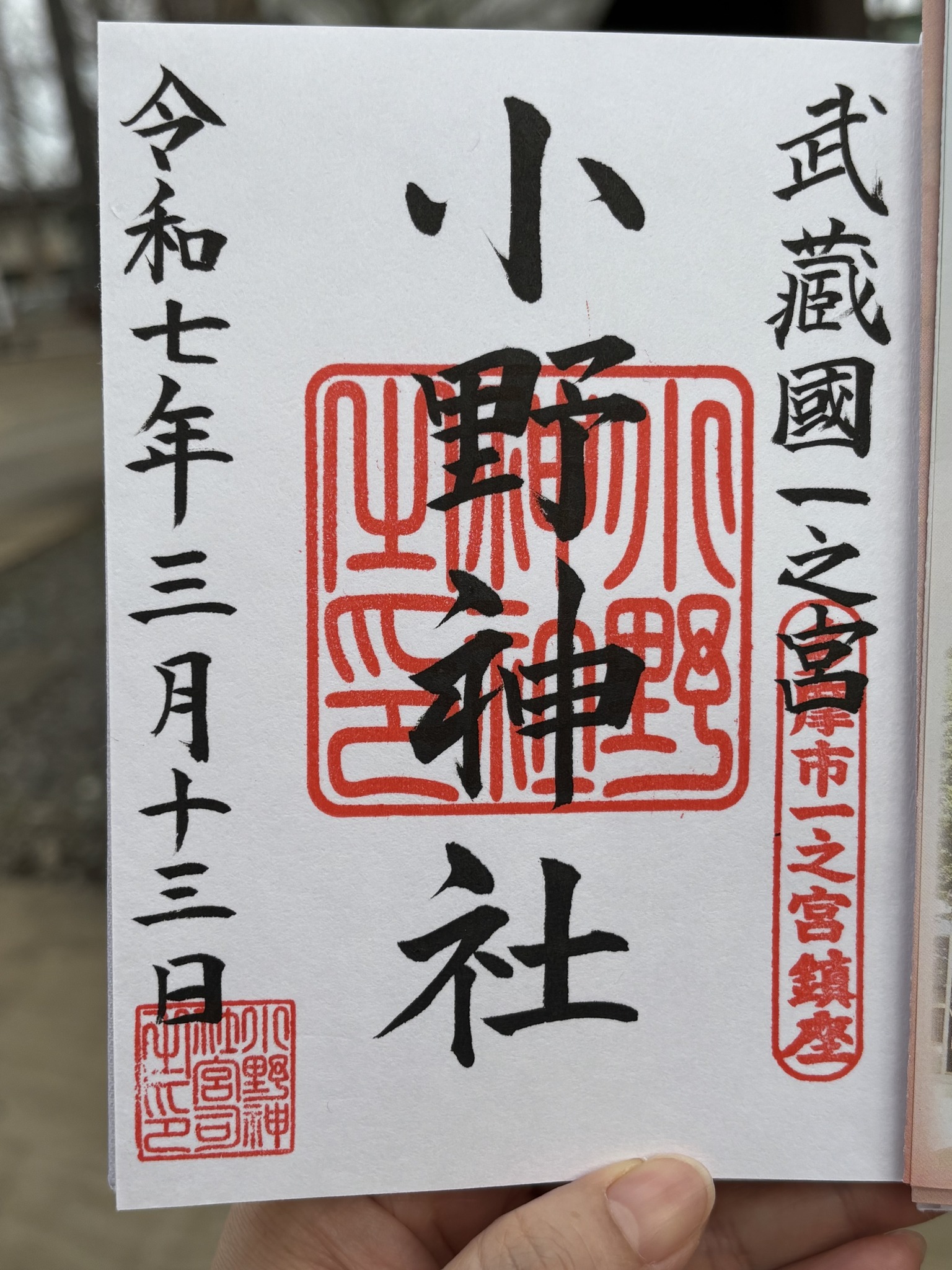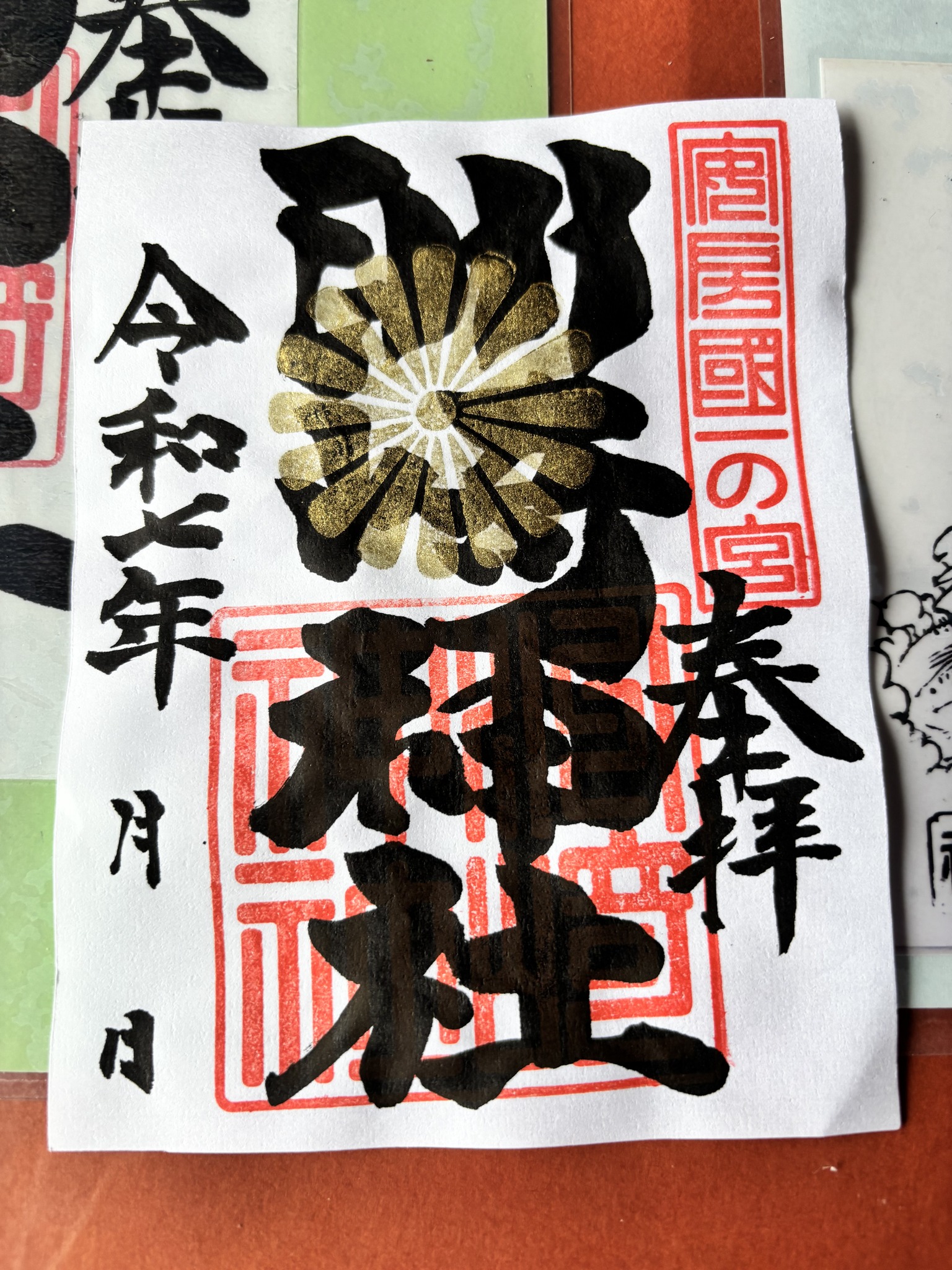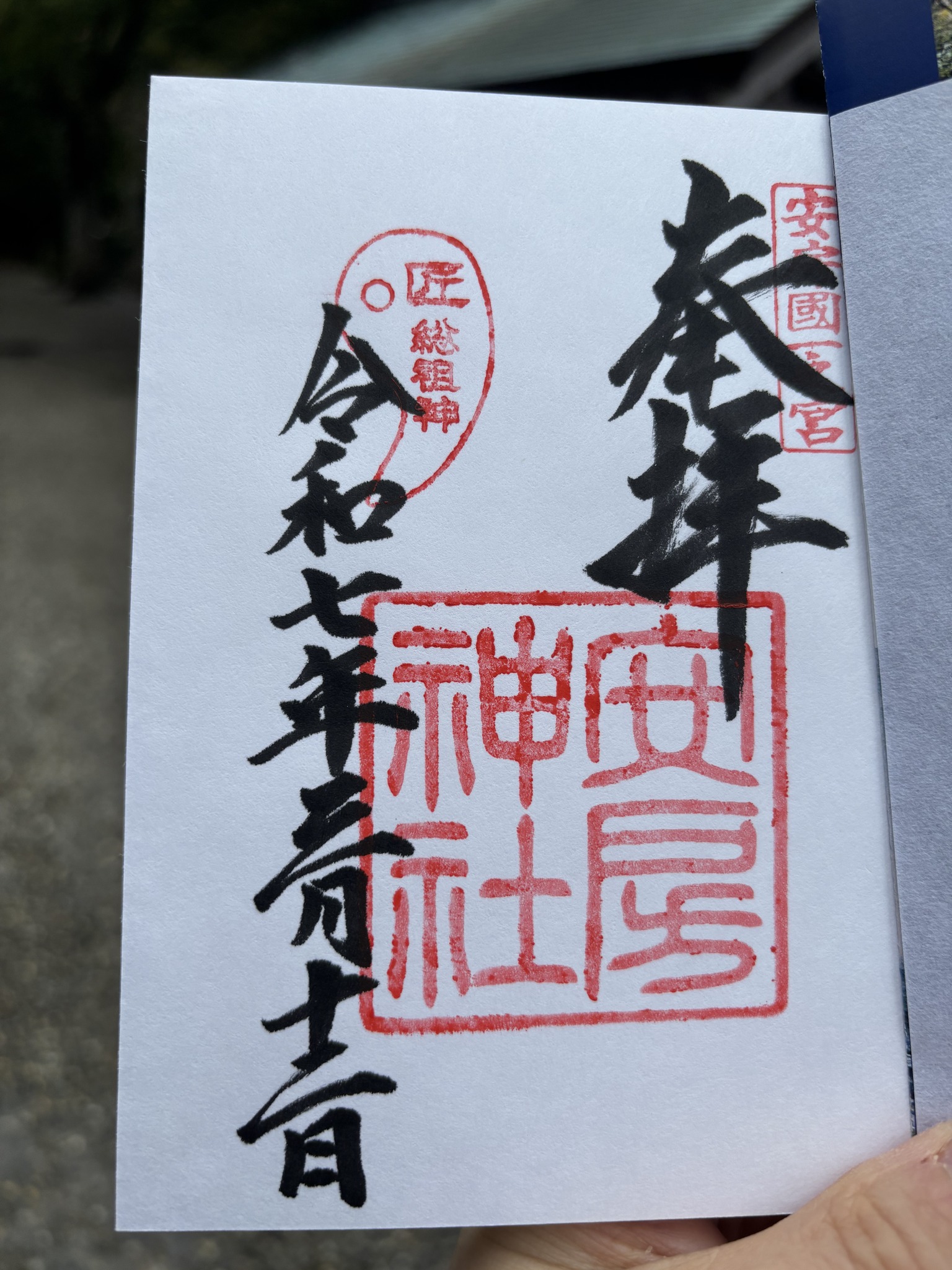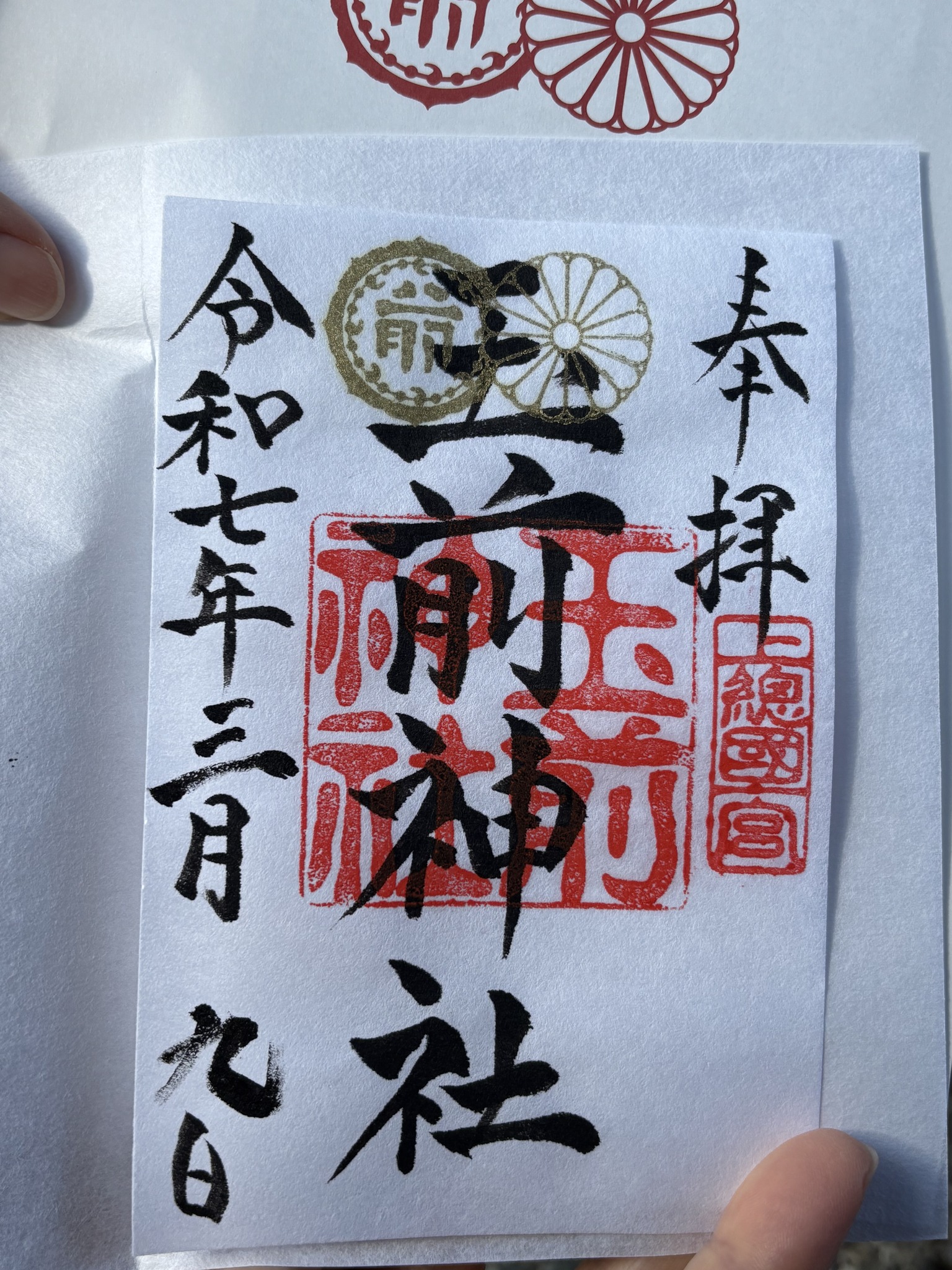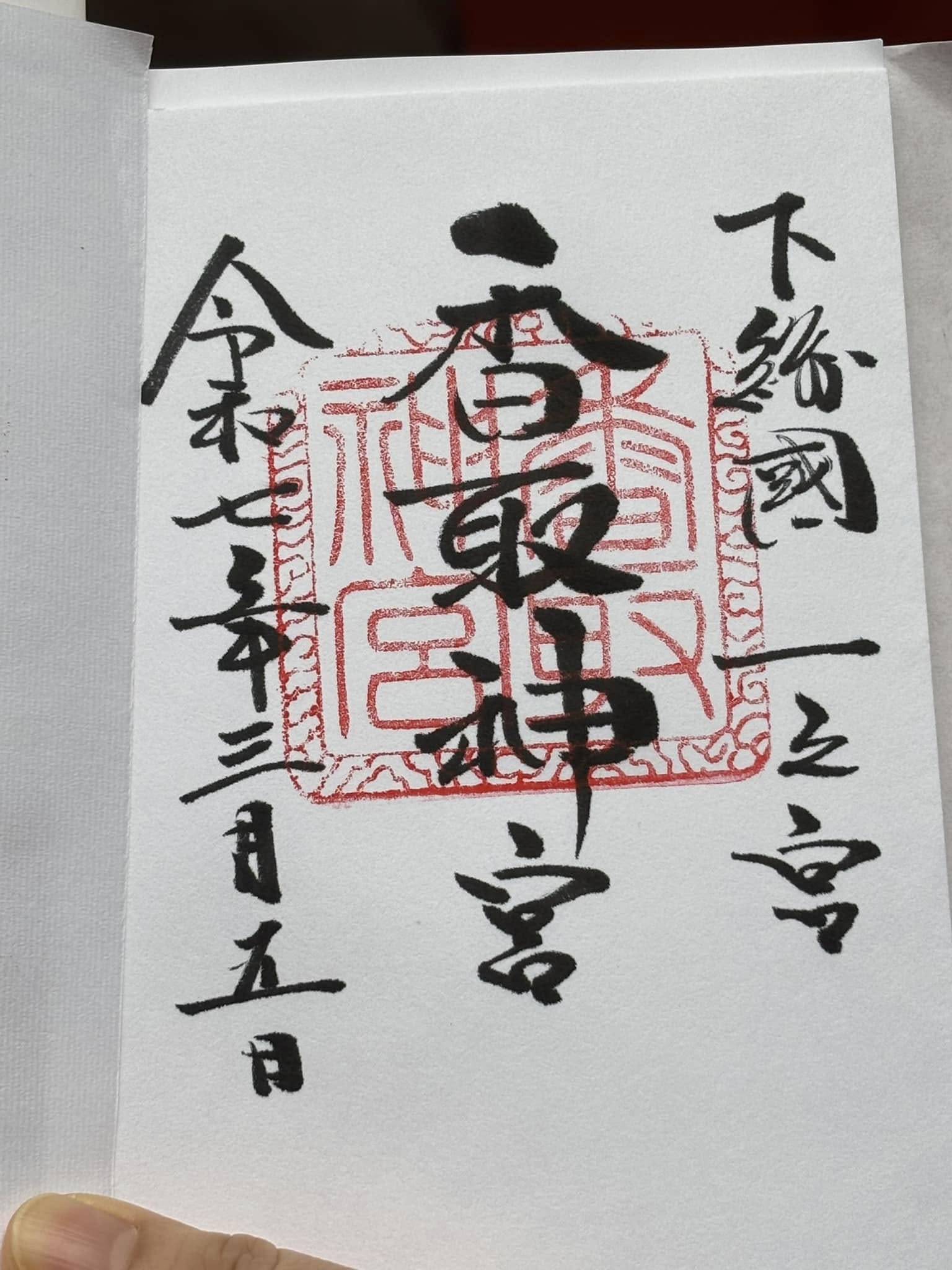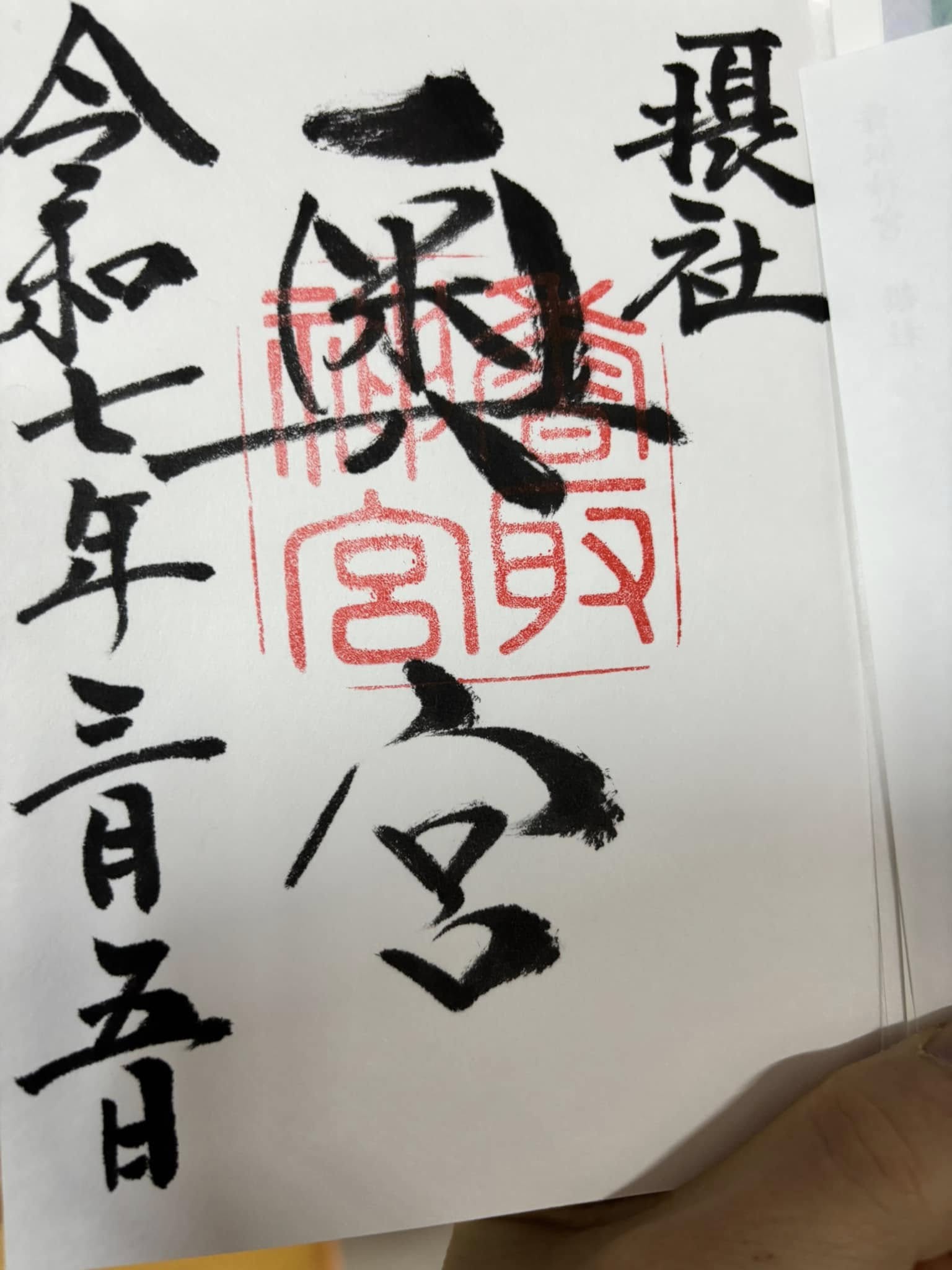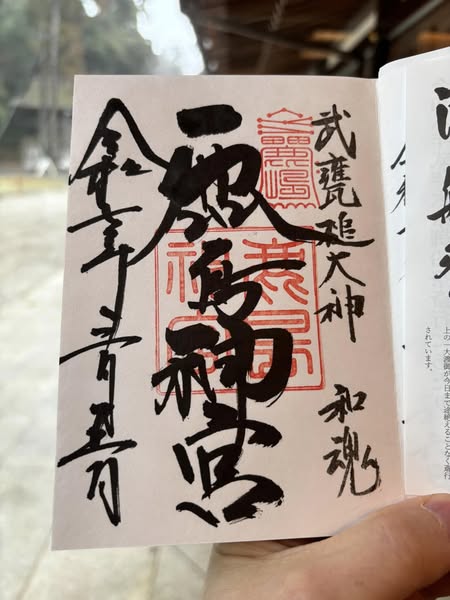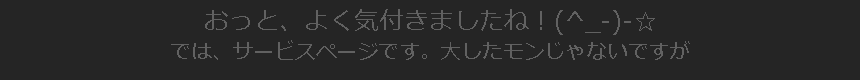「相模の國一之宮」を周ったあと、勢い(ノリ)で「関八州一之宮巡り」もやっちまおうか、って感じでレッツゴー!です
不思議なのが「関八州(関東の8州)にある一之宮(それぞれ一番の神社)」だから8カ所だと思うじゃないですか
調べるとなんと11カ所?12カ所??らしいんですね
ツッコミどころが有る関東の一之宮の数ですが、夫々に理由と格式があるようで、まあ全部行ってみる事にしました
(寒川神社は既に<相模國 六社巡り>で行ってますので割愛です)
|
12-1.【下野の國一之宮(その2)】日光二荒山神社
(ニッコウフタラサンジンジャ) 767年創建:2025/4/9
:栃木県日光市山内 2307
宇都宮の二荒山神社は「フタアラヤマ」、こっちの日光の二荒山神社は「フタラサン」、読みが違います
宇都宮よりも400年以上後に、天台宗の勝道上人により日光に出来た神社なので(別の神様)、宇都宮との区別のため「ニッコウフタラサンニンジャ」と呼ばれるようです
まあ、基本的に音読みするのが「仏教」ですので・・・
本社(中宮祠)は東照宮の左隣(:日光市山内中宮祠2484)にありますが、
二荒山別宮 本宮神社(ホングウジンジャ):日光市山内2383
二荒山別宮 瀧尾神社(タキノオジンジャ):日光市山内(番地ナシ)
本宮神社は国道119号神橋信号丁字路正面の森の中、
瀧尾神社は県道247号の稲荷川橋を渡る直前に左折して細い道を1kmほど進んだ森の中
(ヤマビル注意!)にひっそりと佇んでいます
三社まとめて「日光三社」と言われていますね
※三社の御朱印は、すべて本社(中宮祠)社務所で頂きます!(ずるして三社回ってないのに三社分頂いちゃダメですヨ)
|

|

|
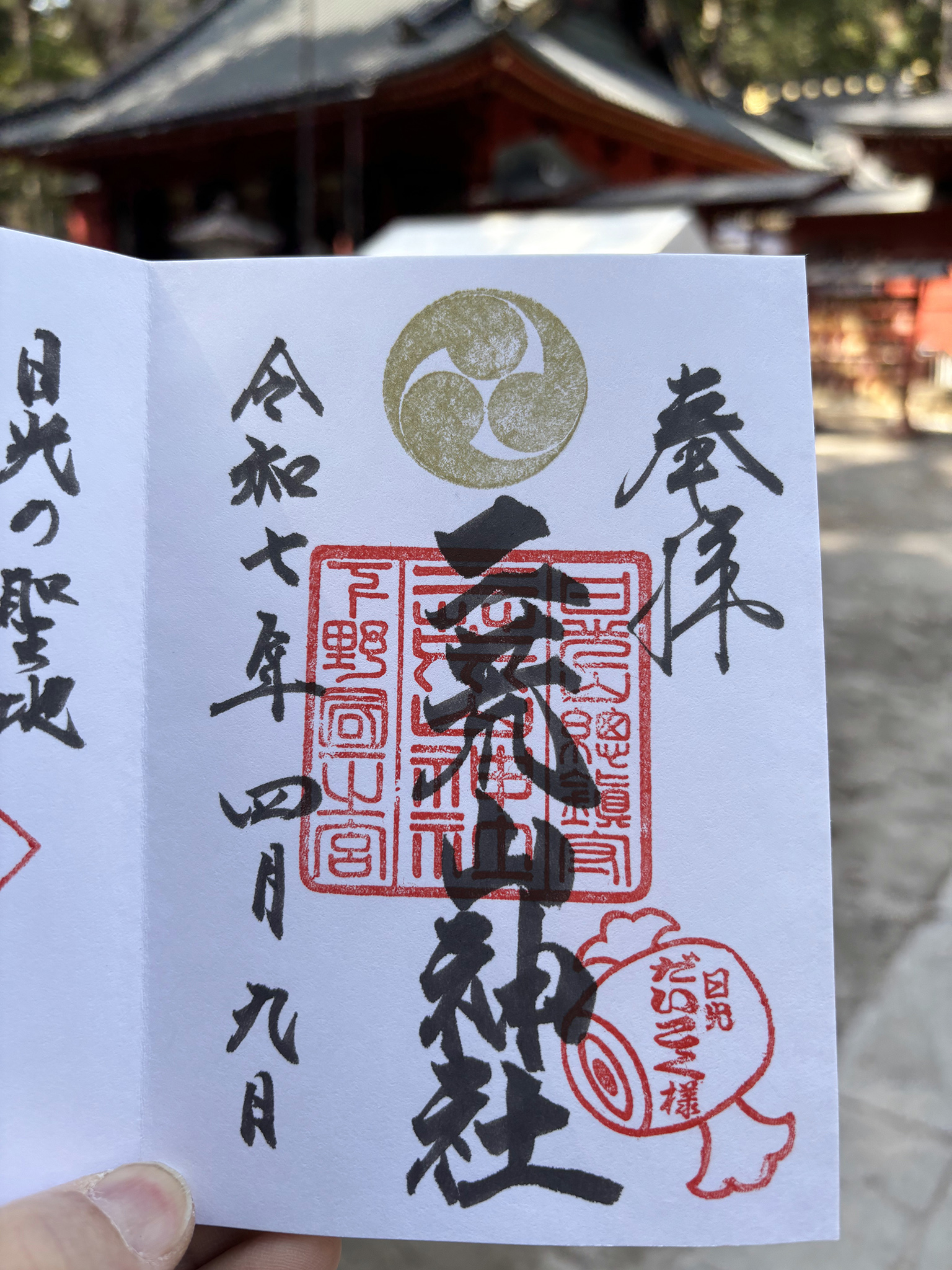
|
|
12-2.【日光二荒山神社別宮 本宮神社】(ホングウジンジャ)
808年創建:2025/4/9
:日光市山内2383
|

|

|
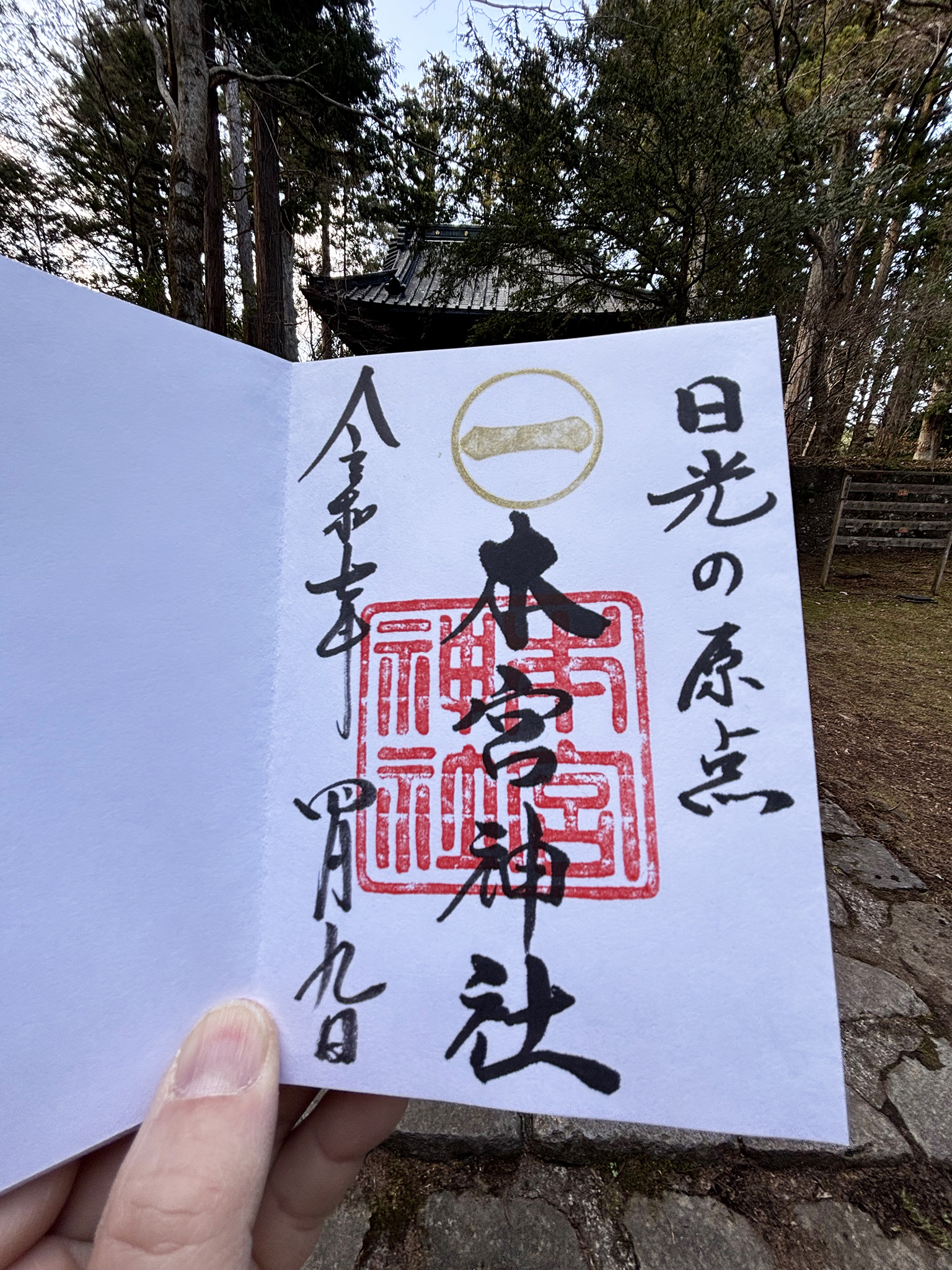
|
|
12-3.【日光二荒山神社別宮 瀧尾神社】(タキノオジンジャ)
820年創建:2025/4/9
:日光市山内(番地ナシ)
ヒル出没注意!だそうで、梅雨とか雨上がりはヤバそうです
|

|

|
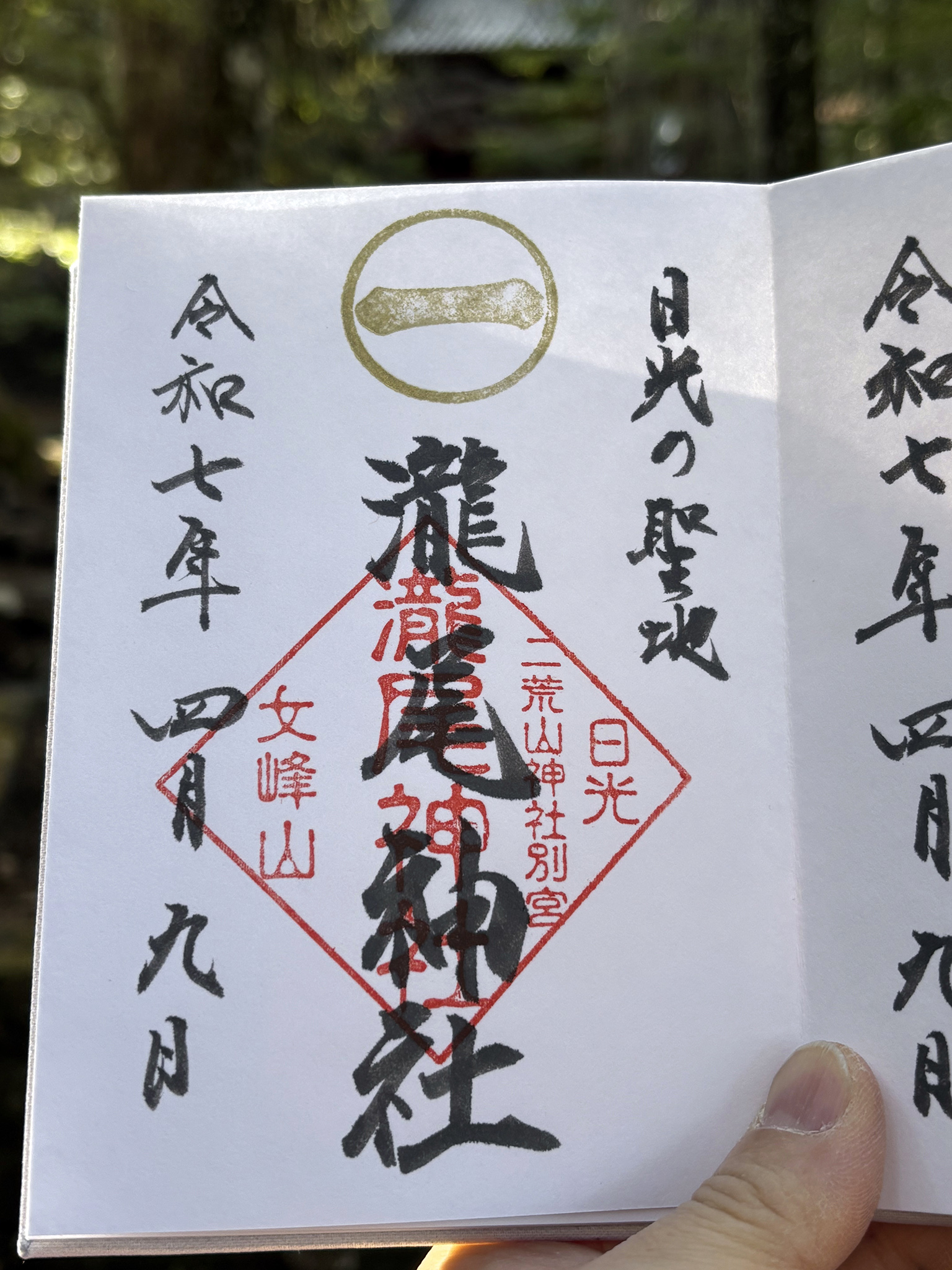
|

鳥居「運試しの鳥居」があって、その右に丸いボールが入った箱と賽銭箱があるので、
幾許かのお賽銭を入れてボールを3つ取り出し、鳥居の上の真ん中に開いている円い穴にボールを1コでも通すと願いが叶うと言われてます
見上げて投げて小さな穴に通すって、距離感が掴めずまったく無理!でしたよ(笑)
|
中宮祠の御祭神:大己貴命(オオナムチノミコト):父
瀧尾神社御祭神田心姫命(ダゴリヒメノミコト):妻
本宮神社御祭神:味耜高彦根命(アヂスキタカヒコネノミコト):子
★ページのトップへ戻る
|
11.【下野の國一之宮(その1)】宇都宮二荒山神社
(ウツノミヤフタアラヤマジンジャ) 353年創建:2025/3/30
:宇都宮市馬場通り 1-1-1
下野(シモツケ)の國一之宮も2カ所あります
もう1カ所は「日光二荒山神社」です
日曜日にまたまた思い立って仕事終わりの午後に出発したので、
宇都宮のあと日光へ行くには行きましたが社務所が16:00終了のため
日光二荒山神社の御朱印は、無念でした(後日リベンジ)
で、宇都宮二荒山神社は宇都宮市街の中心にある有名な神社ですが、
御朱印は直接書いて頂くのではなく予め書いた紙を渡され「御朱印帳に貼ってね」パターンです
|

|

|

|
御祭神:豊城入彦命(トヨキイリヒコノミコト)
★ページのトップへ戻る
|
10.【上野の國一之宮】貫前神社(ヌキサキジンジャ)
531年創建:2025/3/27
:群馬県富岡市一ノ宮1535
やっと上野の國(コウズケノクニ)へ(笑)
午前中の仕事終わりに行きたくなり、ちょっと無理があるかな?と思いましたが、閉門20分前に到着しました(;^_^A
圏央道周りで220kmの距離は、午後から行くにはかなりキツいですね
ここは富岡製糸場に近い山にありますが、山頂ではなく少し窪んだところにお社があるので、お参りするのに「階段を下って行く」という今までに無いシチュエーションで、「さすが一之宮」の佇まいですが、なぜ下り参道になっているのか「正確な理由が伝わっていない」とか
ちょうど桜が満開でした
|

|

|

|

|
御祭神
:経津主神(フツヌシノカミ)
:姫大神(ヒメオオカミ)
★ページのトップへ戻る
|
9.【武蔵の國一之宮(その3)】氷川女體神社(ヒカワニョタイジンジャ)
崇神天皇在位中(紀元前97~30年)に創建:2025/3/20
:さいたま市緑区宮本2-17-1】
こちらが須佐之男命の奥様「稲田姫命」が祭られている神社ですね(體=体の旧字体です)
そして二人の子の大己貴命は、中山神社(中氷川神社) で祭られていて、氷川神社+氷川女體神社+中山神社の三社で一体の氷川神社を形成しているそうです
割烹着着たおばあちゃんが御朱印帳を書いてくださいました
※中山神社は一之宮ではないので別の機会に
|

|

|
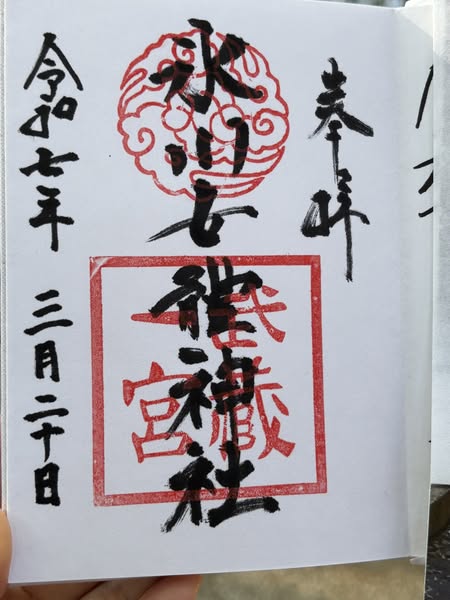
|
8.【武蔵の國一之宮(その2)】氷川神社(ヒカワジンジャ)
紀元前350年前後に創建:2025/3/16
:さいたま市大宮区高鼻町1-407
数多ある他の氷川神社と区別するために”大宮”氷川神社と言われたりもするようです
御祭神は
須佐之男命(スサノオノミコト):夫
稲田姫命(イナダヒメノミコト):妻
大己貴命(オオナムチノミコト):息子
ですが
稲田姫命は3.氷川女體(体)神社の御祭神でもあるので
氷川神社を「男体社」、氷川女體神社を「女体社」として対を成すとの事で、
氷川女體神社も武蔵の國一之宮らしいのかな(^-^;
|

|

|
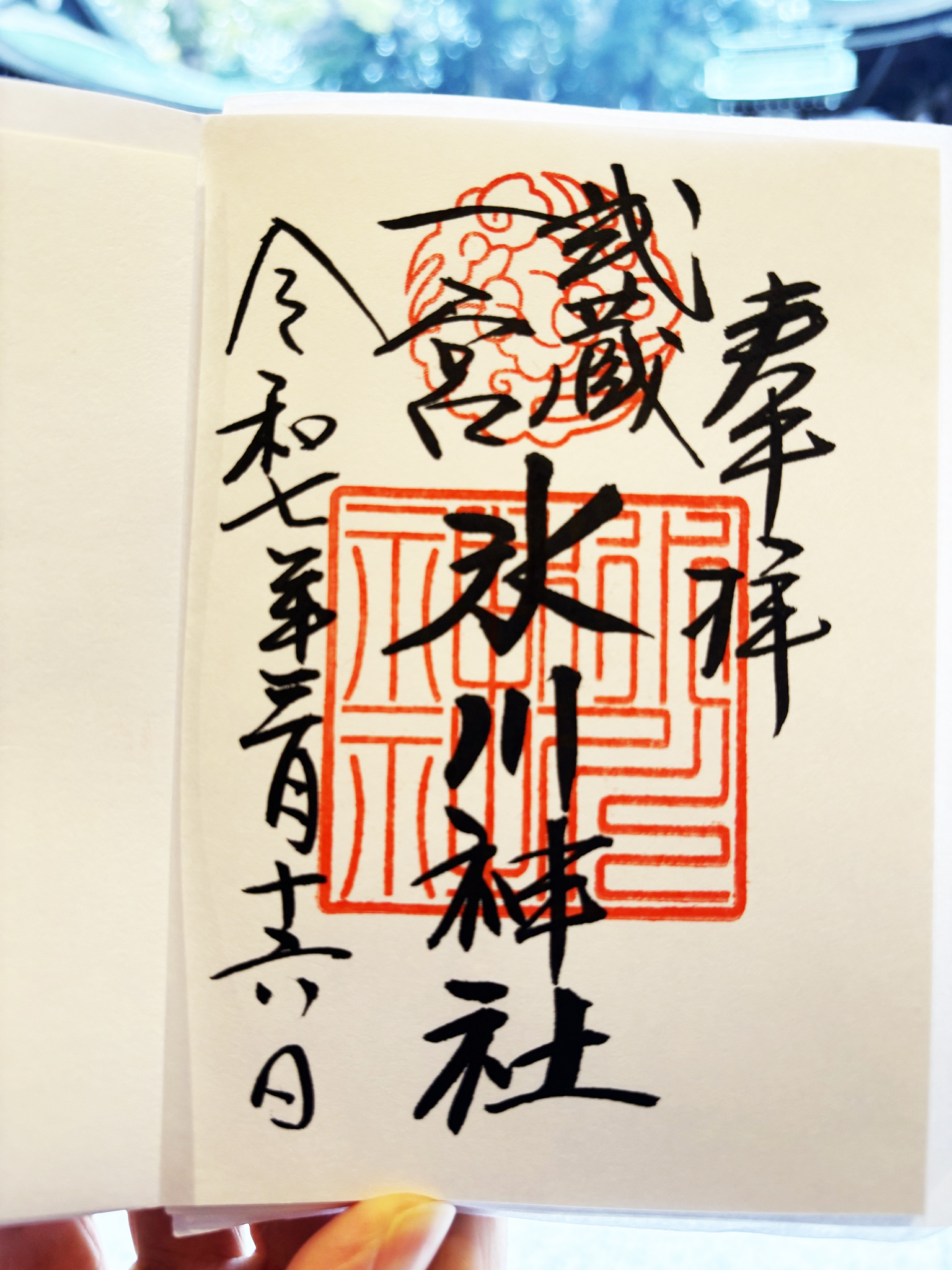
|
★ページのトップへ戻る
|
武蔵の國一之宮、3カ所ありますΣ(・□・;)
7.【武蔵の國一之宮(その1)】小野神社(オノジンジャ)
紀元前531年創建?:2025.3.13
:多摩市一ノ宮1-18-8
住所は多摩市一ノ宮なので、確かに武蔵の國一之宮で間違い無いですが、
風格は普通の郷社でした
|

|

|
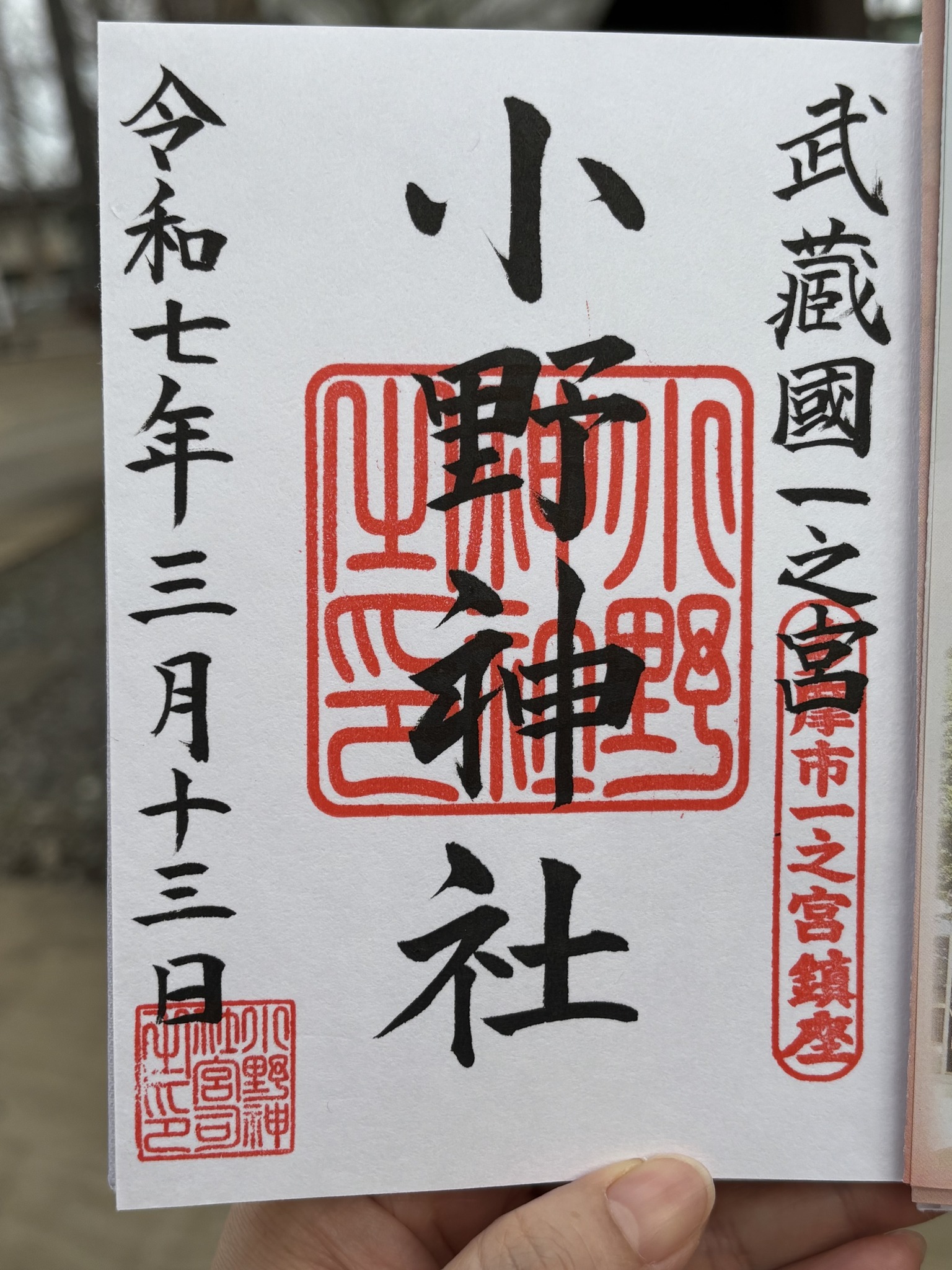
|
御祭神
:天下春命(アメノシタハルノミコト)
:瀬織津姫命(セオリツヒメノミコト)
★ページのトップへ戻る
|
6.【安房の國一之宮(その2)】洲崎神社(スザキジンジャ)
717年創建?:2025/3/12
:館山市洲崎1344
高台にあって(150段以上の石段を上る)晴天の日は富士山を望めるのですが、行った日はあいにくの雨でした(郷社っぽい)
御朱印は、おみくじみたいに無人の引き出しに入っている2種類のうち1種類を500円と交換で持って帰り「御朱印帳に貼ってね」パターンです(週末は巫女さんか神主さんが居て書いて下さるのか不明ですが、ちと侘しかった)
|

|

|

|
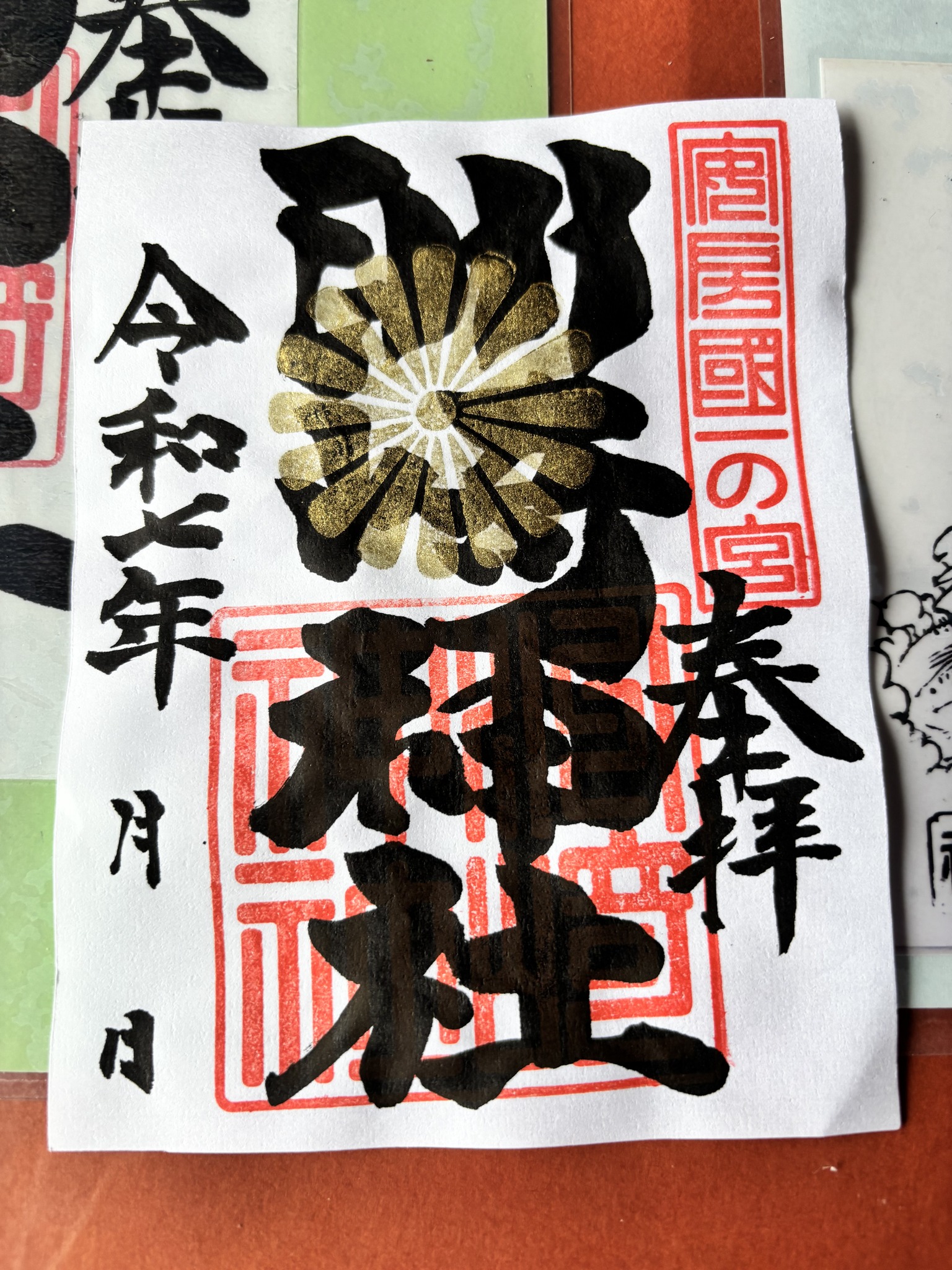
|
御祭神:天比理乃咩命(アマノヒリノメノミコト)
安房神社「天太玉命」の后神(奥様)のようです
さて、安房の國一之宮は2カ所あります
一之宮は本来その地方の一番の神社なので「一カ所」のはずなのですが・・・
5.【安房の國一之宮(その1)】安房神社(アワジンジャ)
紀元前660年創建:2025/3/12
:館山市大神宮589
森に囲まれた厳かな感じで、ここもただならぬ雰囲気のある神社です
|

|

|
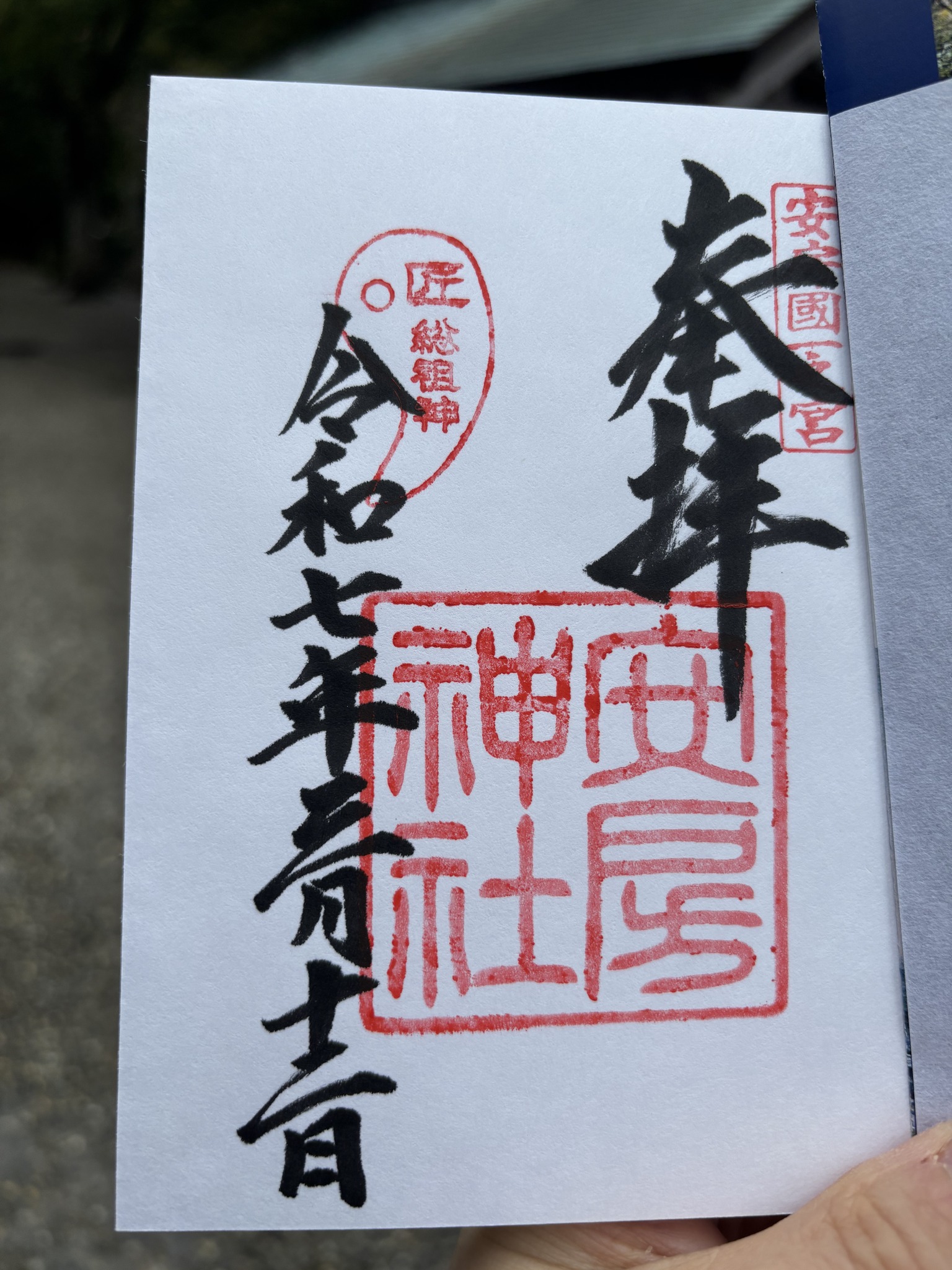
|
御祭神:天太玉命(アメフトダマノミコト)
★ページのトップへ戻る
|
4.【上総の國一之宮】玉前神社(タマサキジンジャ)
1687年創建 2025/3/9
:長生郡一宮町一宮3048
ここのお社は、珍しく”黒い”んですね
鹿島神宮だけでなく、ここにも「さざれ石」があります
それと、ここは御朱印帳に直接書いて頂けず、予め書いてある紙を「御朱印帳に貼ってね」パターンです
なんか切ない・・・
|

|

|
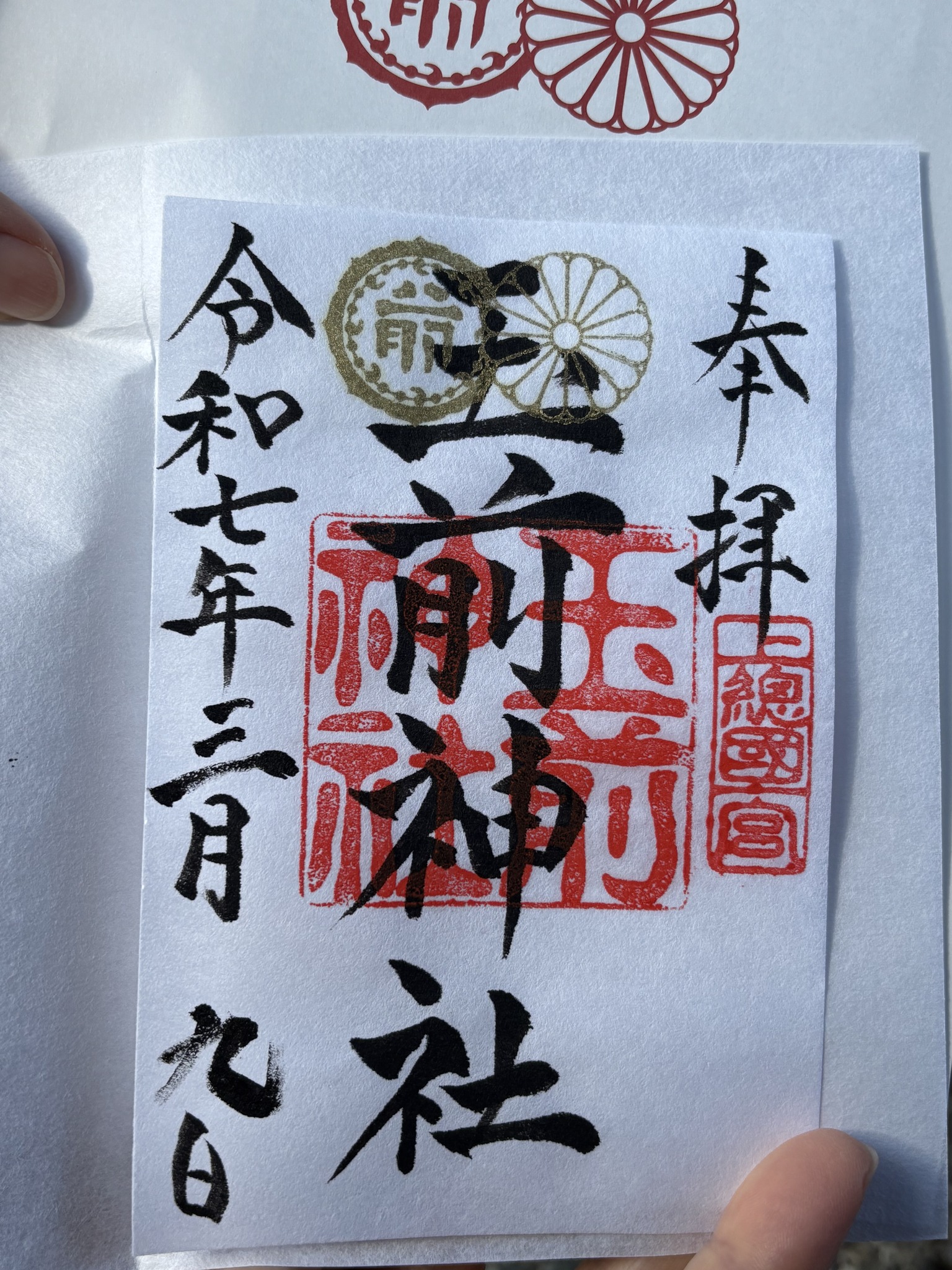
|

|
御祭神:玉依姫命(タマヨリヒメノミコト)
★ページのトップへ戻る
|
3.【下総の國一之宮】香取神宮(カトリジングウ)
紀元前643創建:2025/3/3
:千葉県香取市香取1697
千葉の香取神宮は茨城の鹿島神宮から15kmほどしか離れていないので、同じ日に行って来ました(という事は、ナマズの全長は15km?)
こちらも鹿島神宮同様の「神宮」なので、格式が最上位(格式の高い順に、神宮・宮・大神宮・大社・神社・社)です
※『延喜式神名帳』(←よくわかりません)で最も格式が高い神宮に分類されているのが
<伊勢神宮>
<鹿島神宮>
<香取神宮>
の3神宮らしいです
|

|

|

|
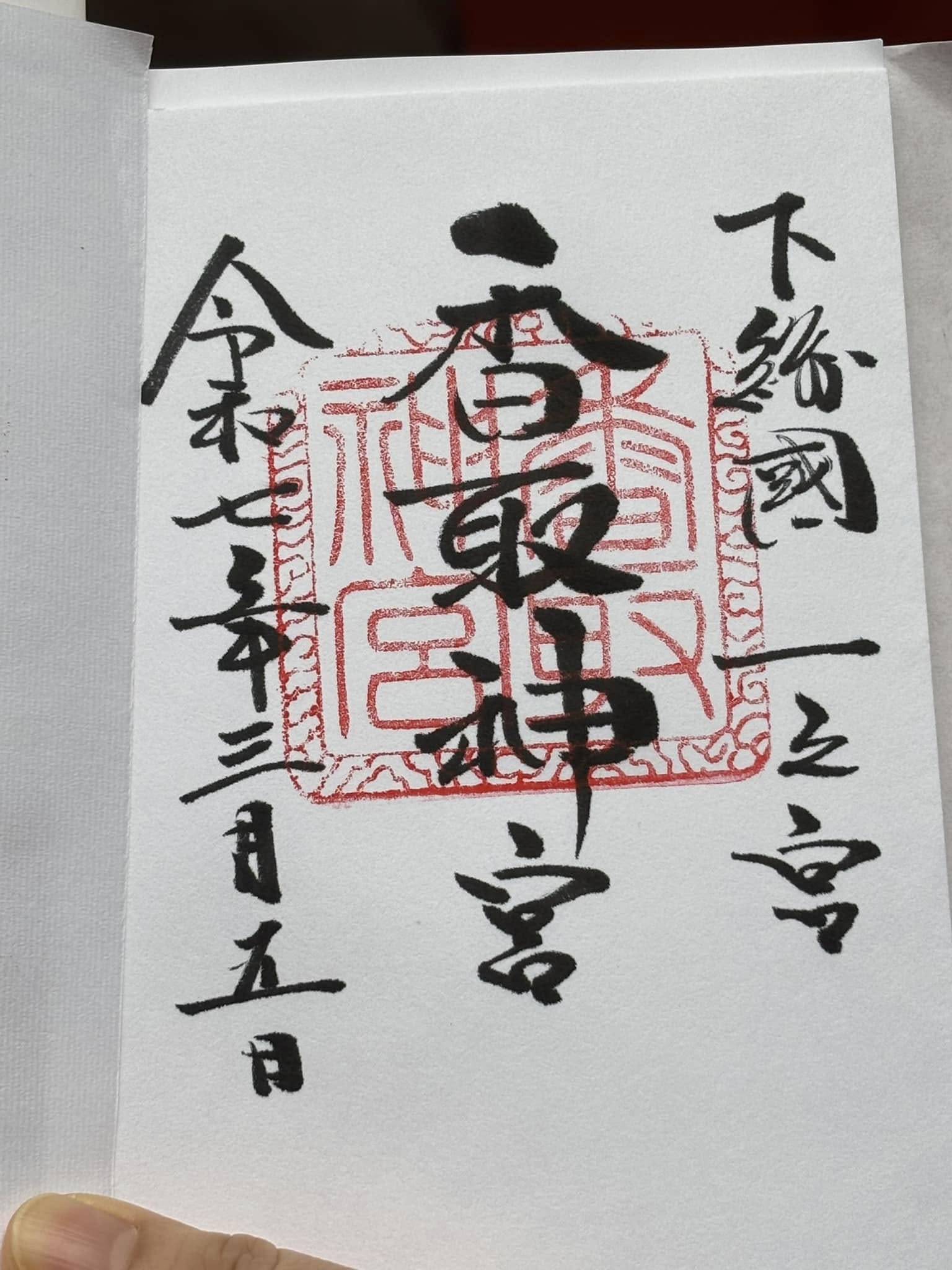
|
|
香取神宮は「奥宮(おくのみや)」↓の方にとても強いパワーを感じました
|

|

|
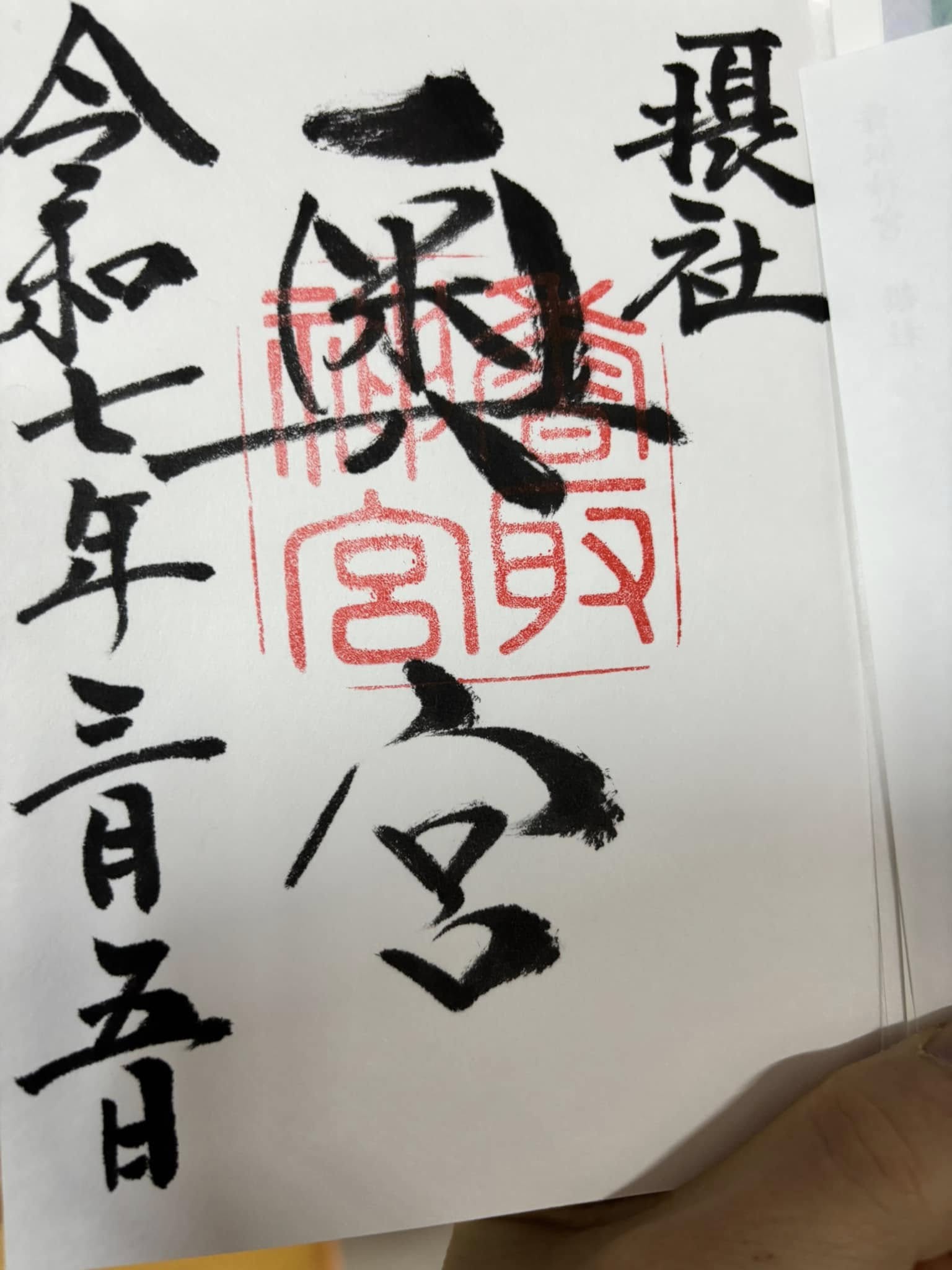
|
御祭神:経津主大神(フツヌシノオオカミ)
又の名:伊波比主命(イハヒヌシノミコト)
奥宮は経津主大神の荒御魂が祀られています
★ページのトップへ戻る
|
2.【常陸の國一之宮】鹿島神宮(カシマジングウ)
紀元前660年創建:2025/3/3
:茨城県鹿嶋市宮中2306-1
武蔵の國以外のまず1カ所目は、常陸の國一之宮(茨城県の一之宮)の鹿島神宮です
要石(ナマズの頭をおさえている)の所は雰囲気がかなり違いますね
※下総一之宮の香取神宮の要石は、ナマズの尾をおさえているらしいです
鹿さんも居るし
さざれ石(君が代の)もあるんですね
|

|

|
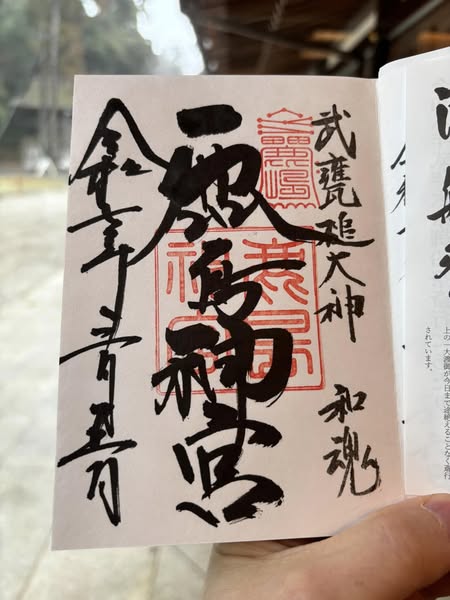
|

|
御祭神:武甕槌大神(タケミカヅチのオオカミ)
★ページのトップへ戻る
|