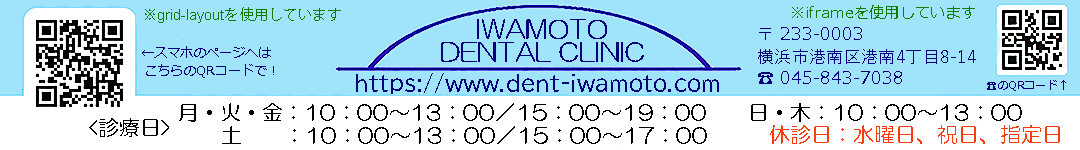<銀歯の作り方>
|
銀歯がどうやって作られるのか、気になりませんか? 先日私が銀歯を製作した時に、画像を撮影しましたのでちょっとご説明しますね。 | |

|
まず、歯を削ったあと歯型を採ります(ココは皆さん経験済みだと思いますので割愛)。 次いで、歯型に石膏を流し込んで模型を作ります。 左図は石膏が固まって歯型から取り出し、周囲をトリミングした状態です。 |

|
模型上でワックスアップします。 左図の紺色のモノがロウ(ワックス)で、窪んでいる部分にロウを盛り足し(アップし)ながら、ちょうど良い形になるように作っていきます。 |

|
出来上がったロウに金属の流し込み口、スプルー(sprue)を付けます。 左図のロウに棒のように付いているのが、スプルーです。 |

|
スプルーが付いたロウ(ワックスアップ)を、円錐台に立てます。 |

|
円錐台にリングを取り付け、リング内壁にライナーを巻きます(この画像では割愛)。 |

|
埋没材を練り、バイブレーターを使って気泡を抜きます。 (これを見ると、いつも液状化現象を想像してしまいます) |

|
リングの中に、気泡を抜いた埋没材を流し込みます。 |

|
埋没材を完全に流し込んだら、固まるまでしばし放置します。 |

|
固まった埋没材から円錐台を外します。 (スプルー側が上を向いている状態) |

|
リング内で固まっている埋没材を、スプルー側を下にしてファーネス(furnace:炉)に入れ、加熱します。 加熱によって、中に入っていたロウが完全に溶けて無くなった状態、つまりスカスカの空洞が出来ます。 |

|
十分に加熱したあとリングを遠心鋳造機にセットして、ルツボに置いた金属を(これは12%金銀パラジウム合金)ガスバーナーで溶解します。 |

|
溶解した金属を、遠心鋳造で流し込みます。 |

|
遠心鋳造したあと、少し冷えるまで時間を置きます。 左図、リング中心に黒っぽく見えるのは、フラックス(flux:融剤)が熱によってガラス化したモノです。ちょっとフラックスを入れすぎちゃいました。 |

|
左図は、埋没材を水に漬けてグズグズにし、金属を取り出したあとの状態です。 |

|
金属に付着している埋没材を完全に取り除き、ちょっと石膏模型に戻してみました。 あとはスプルーの部分をぶった切って、ひたすら研磨するだけです。 |

|
これが研磨し終わった状態です。 ぴったり入って、ピカピカ輝いていますね。 この症例は私が製作・研磨しましたが、通常は技工所へ外注します。 外注技工物の出来の良し悪しは、「ワックスアップ」による形態付与と「研磨」がどれだけ丁寧かどうかで見極められます。 |
|
あとは歯に着けるだけですが、これもみなさん経験済みだと思いますので割愛します。 あっ、ちなみに宝飾品の金属のキャスティングもこんな感じで行われますが、我々の技工作業の寸法精度や研磨精度より数倍、複雑な事をやられています。 デッカい鋳物などは、砂で鋳型を作って、溶けた鉄を流し込んで作ったりしてますヨ。 ★ページのトップへ戻る | |